ENCYCLOPEDIA
アザラシのおもしろ雑学
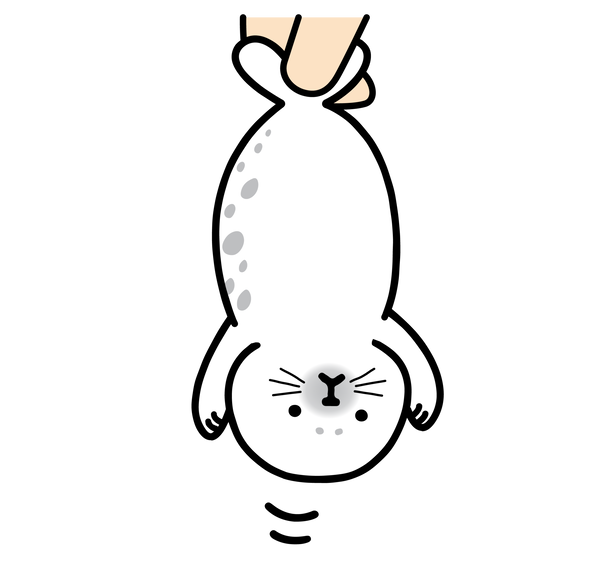
【 アザラシの特徴と生態 】
- 学名
- Phoca largha(ゴマフアザラシ)
- 分類
- 哺乳綱 食肉目 アザラシ科(真・アザラシ類)
- 分布
- 北太平洋および隣接海域(ベーリング海・オホーツク海・日本近海・朝鮮半島沿岸・アラスカ沿岸)
- 体長
- 約1.5〜1.8m(成獣)
- 体重
- 約70〜120kg(季節・性別で変動)
- 食性
- 肉食(魚類・イカ・甲殻類など)
- 寿命
- 野生で約20〜30年/飼育下で30年以上の例
- 保全状況
- IUCNレッドリスト LC 低危険種(種により異なる)
アザラシは四肢がヒレ状に進化した海生の哺乳類で、流線型の体と厚い皮下脂肪で寒海に適応しています。岩礁や流氷で休み、海では優れた潜水能力で魚やイカを捕らえる生活を送ります。ここでは代表種・ゴマフアザラシを軸に、アザラシの特徴や生態、文化的背景を雑学的にわかりやすく紹介します。
ENCYCLOPEDIA アザラシの雑学
見た目と適応
- 丸みのある流線型の体は水中での抵抗を最小化。皮下脂肪(ブレバー)が断熱と浮力に貢献します。
- 前・後肢はヒレ状。真・アザラシ類は後肢を前方に折り畳めず、陸上では“ずり這い”で移動します。
- ゴマフアザラシの体表は灰色地に黒い斑点(ゴマ模様)。個体識別に使われます。
潜水のしくみ
- 潜水時は心拍数を落とし(ダイビング・リフレックス)、血流を脳や心臓へ優先配分して酸素を節約します。
- ヘモグロビン・ミオグロビンが豊富で、体内に酸素を多く貯蔵できます。
- 多くの種が数十〜数百mの潜水に適応。ゴマフも数分〜10数分の潜水が一般的です。
食性と狩り方
- 主食は小〜中型魚類(ニシン類・タラ類など)やイカ・甲殻類。季節や海域でメニューが変わります。
- ヒゲ(感覚毛:バイブリッサ)が水流の乱れを捉え、暗所や濁水でも獲物の動きを察知できます。
- 一部の個体群では協調的に魚群を追い込む行動も観察されます。

生活史と繁殖
- 流氷・砂浜・岩礁などで休息と換毛(年1回程度)を行い、体表の保温・防水性を回復します。
- 繁殖期は種・海域で差がありますが、氷上や陸上で出産。白い産毛(ラヌーゴ)を持つ仔が生まれる種も。
- 授乳期間は数週間程度と短期集中型。高脂肪乳で仔を効率よく成長させます。
コミュニケーションと知覚
- 鳴き声や体の姿勢、匂いで意思疎通。繁殖期にはオスが音声やディスプレイでアピールします。
- 水中聴覚に優れ、低周波音にも敏感。ヒゲは“水中レーダー”のような役割を果たします。
- 視覚も良好で、薄明かりの海中でも行動可能。陸上では色覚は限定的とされます。
文化と保全
- 北方文化圏では衣食・民話・アイデンティティと深く結びついてきました。
- 近代以降は漁業との資源競合、混獲(網にかかる事故)、海洋汚染(マイクロプラスチック・油)などが課題。
- 種により保全状況は幅広く、地域個体群レベルでのモニタリングが重要です。
色々なトリビア
- “アシカ”との違い:アシカは外耳介があり後肢を前に折って陸を歩けますが、アザラシは耳介が目立たず陸上は腹ばい移動。
- 換毛期は体色や模様のコントラストが変わり、写真映えが増す季節です。
- ヒゲ1本1本に血管と神経が通り、獲物の“尾びれが作る渦”まで感知するとされます。
まとめ
アザラシは寒海に特化した海生哺乳類で、潜水生理・感覚毛・厚い皮下脂肪といった洗練された適応を備えています。代表種ゴマフアザラシを通して見ると、海と陸を行き来する生活史の巧妙さが際立ちます。


